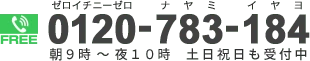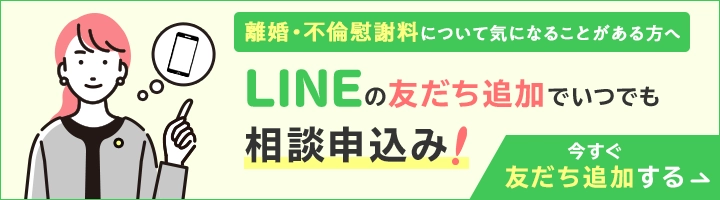親権・監護権とは?離婚時に親権者を取り決める方法や考慮される要素

離婚条件にはさまざまなものがありますが、子どもの親権は、離婚の際に必ず取り決めなければなりません。
親権者は、「母親だから」、「父親だから」という理由だけで決まることはなく、さまざまな事情を考慮して決める必要があります。
このページでは、親権の基礎知識に加え、親権と監護権の関係、親権の決め方などについて解説します。親権を認めてもらうためにも、「親権・監護権」について正しく理解しておきましょう。
目次
このページでわかること
- 親権・監護権の基礎知識
- 親権者を決める際に考慮される要素
- 親権者を取り決める方法
親権とは?
親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負っている一切の権利・義務のことです。
未成年の子どもがいるケースでは、親権者を決めないと離婚できません。
離婚届にも親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届自体を受け付けてもらえないのです。
単独親権と共同親権
親権には、「共同親権」と「単独親権」の2種類があります。
共同親権とは、父母の双方が親権を持つ制度のことで、単独親権とは、父母のどちらか一方のみが親権を持つ制度のことです。
現在の日本では、原則として結婚している父母にのみ共同親権が認められており、離婚後の共同親権は認められていません。
そのため、離婚するときは父母のどちらか一方を単独の親権者として定める必要があります。
なお、2024年に離婚後の共同親権を導入する民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正案は、2026年までに施行される見通しです。
親権を構成する要素
親権は、大きく分けて以下の2つの内容で構成されています。
- 財産管理権
- 身上監護権
さらに、「財産管理権」と「身上監護権」にはそれぞれ以下のような権利が含まれています。

それぞれ詳しく見ていきましょう。
財産管理権
財産管理権とは、未成年の子どもの財産を管理し、子どもの代わりに法律行為を行う権利・義務のことです。具体的には、以下の権利が含まれます。
| 財産管理権 | 財産を包括的に管理・処分する権利 |
|---|---|
| 法律行為の代理権 | 子どもに代わって法律行為を行う権利 |
| 法律行為の同意権 | 子どもの法律行為に同意を与える権利 |
これにより親権者は、子どもの代わりに預貯金口座を開設することや、祖父母から贈与を受けることなどができます。
ただし、どんな法律行為でも自由に行えるわけではありません。
たとえば、子どもの同意を得ずにアルバイトの労働契約を結ぶことや、子ども名義で借入をする行為などはできないため注意が必要です。
身上監護権
身上監護権とは、子どもと一緒に生活をして、子どもの世話や教育をする権利・義務のことです。具体的には、以下の権利が含まれます。
| 居所指定権 | 子どもの居所を指定する権利 |
|---|---|
| 職業許可権 | 子どもの職業を許可する権利 |
| 身分行為の代理権 | 子どもが行う身分法上の行為に対する同意や代理をする権利 |
なお以前は、これらのほかにも子どもの懲戒・しつけをする権利である「懲戒権」が認められていました。
しかし、懲戒権が体罰などの口実に使われていたため、令和4年の民法改正で懲戒権が削除され、体罰や児童虐待の禁止が明文化されました。
親権と監護権
監護権とは、親権を構成する要素の一つである「身上監護権」のことです。
つまり、子どもと一緒に生活をして子どもの世話や教育をする権利・義務のことを指します。
監護権は親権の一部であるため、基本的には親権者が行使します。
ただし、以下のように親権者と監護権者を分けて考えるケースもあります。
親権者と監護権者の違い
親権者は、離婚するときに必ず決めなければなりません。一方で、監護権者は離婚したあとで決めることもできます。
また、婚姻中は共同親権のため、父母のどちらか一方のみが親権者になることは法律上あり得ません。
しかし、離婚前に夫婦が別居するケースでは、父母のどちらが子どもの面倒を見るか決める必要があります。そのため、離婚前であっても父母のどちらか一方のみが監護権者になることはあり得ます。
なお、監護権者になるための監護権者指定の手続は、親権者指定・変更の手続とほとんど同じです。子どもの利益・福祉を中心に考え、監護権者を決めることになります。
親権者と監護権者を分けるケース
親権と監護権は、原則として同一の親に帰属しますが、例外的に別々に定めることも可能です。
親権者が子どもを監護できない事情がある場合や、親権者でない一方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることもあり得ます。
たとえば、以下のようなケースです。
- 親権者である父親が海外出張のため子どもの世話や教育がまったくできない
- 財産管理は父親が適任であるが、幼い子どもの世話をするうえでは母親が適任
- 親権争いに折り合いがつかず、子どもの精神的・肉体的な成長に悪影響がある など
ただし一般的には、親権者と監護権者は一致したほうが、子どもの利益・福祉に資すると考えられています。
親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット
親権者と監護権者を分けることには、以下のようにメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
特に監護権者は、子どもの財産管理や法律行為を代わりに行うことはできません。そのため、さまざまな場面で親権者の同意が必要になります。
たとえば、子ども名義の預貯金口座を開設することにも、その都度親権者の同意が必要です。
父母間で子どもに関する方針が違うとトラブルに発展する可能性もあるため、親権者と監護権者を分けるべきかどうかは慎重に判断すべきでしょう。
親権者になるためには?
特に裁判などで親権者を決める際には、「親権者としてふさわしい」と認めてもらうことが重要です。
親権者としてふさわしいかどうかの判断は、子どもの利益を中心に考えなければなりません。
以下で、親権者を指定する際に考慮される要素と、影響しない要素をそれぞれ見ていきましょう。
親権者を決める際に考慮される要素
親権者を決める際には、主に以下のような要素を考慮して、総合的な判断がなされます。
- 子どもに対する愛情
- 監護実績・監護の継続性
- 健康状態や監護能力
- 収入などの経済力
- 子どもの年齢・性別
- 離婚後の生活・子育ての環境
- 面会交流ができるかどうか
- 兄弟姉妹が分かれないかどうか
- 子ども本人の意思(年齢による)
なかでも、これまでの監護実績や監護の継続性は特に重要視される傾向があります。
これは、「これまで子どもの世話をしてきた親を親権者にすれば、離婚後も安定した養育を行える可能性が高い」と考えられるためです。
ただし、監護実績をつくるために無理やり子どもを連れて別居するなどの行為はしてはいけません。
状況によっては「子どもを連れ去った」として、親権者としての適格性を判断するうえで大きなマイナスとなることもあります。
親権者を決める際に影響しない要素
親権者としてふさわしいかどうかの判断において、「不倫(不貞行為)したこと」はそれほど影響しません。
これは、親権者を決める際には「子の福祉(利益)」がもっとも重要であり、夫婦間のトラブルと親権の判断は別問題であると考えられるためです。
そのため、不倫をしたという事情だけで親権者としてふさわしくないと判断されることはないでしょう。
ただし、不倫相手に会いに行くために子どもを家に一人で放置していたなど、不倫自体が子どもに悪影響を与えた場合は、親権者としてふさわしくないと判断されることもあります。
親権者を取り決める方法
親権者は、以下のいずれかの方法で定めます。
以下で詳しく見ていきましょう。
①夫婦間で話し合う
まずは、夫婦で離婚するかどうかや、親権者をどちらにするか話し合いましょう。
親権者を決める際には、「どちらの親と暮らすことが、子どもの幸せにつながるか」ということを最優先に考えることが大切です。
話合いで親権者が決まった場合には、子どもの養育費や面会交流についても併せて取り決めておくことをおすすめします。
また、取り決めた内容は書面にまとめ、離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書を作成しておけば、合意内容を守る義務が生じ、あとで「言った・言わない」のトラブルになることも防げます。
②離婚調停を申し立てる
話合いがまとまらない場合や、配偶者が話合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停では、調停委員を介して離婚自体や親権をはじめとする離婚条件について話し合います。
合意できれば調停が成立し、取決めの内容をまとめた調停調書が作成されます。
③離婚裁判を提起する
調停で合意できない場合は、最終的に裁判で親権者を決めることになります。
裁判では、これまでの経緯や夫婦それぞれの主張、証拠などをもとに、裁判所が親権者としてふさわしいほうの親を判断します。
なお、裁判で15歳以上の子どもの親権を定める場合、裁判所は子ども本人の考えや意思を聞かなければなりません
そのため、ある程度年齢の高い子どもであれば、親権の決定において子ども自身の意思が重要になるといえるでしょう。
親権者の変更
親権者は、裁判所が「子の利益のために必要がある」と認めない限り、基本的に変更できません。
しかし、以下のような特別な事情がある場合には、裁判所に申し立てることで親権者を変更できる可能性があります。
- 親権者が子どもの育児放棄・虐待をしている
- 親権者が重大な病気・死亡・行方不明になっている
- 15歳以上の子どもが親権者の変更を希望している
- 親権者の海外転勤や多忙で子どもの世話が難しくなった など
このような特別な事情があり、親権者を変更したい場合は、親権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てましょう。
親権に関するよくある質問
親権について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。
親権は子どもが何歳になるまで有効ですか?
親権がおよぶのは、子どもが成人(18歳)するまでです。
親権が消滅すると、子どもは自分の意思で法律行為(契約など)や居所・職業の決定を行えるようになります。
親権者を決めるとき母親は有利ですか?
子どもが乳幼児である場合は、監護の中心的な存在である母親が親権者として指定されることが多いです。
しかし、さまざまな要素が考慮されるため、「母親だから」というだけで常に有利というわけではありません。
母親が「親権者としてふさわしくない」と判断されれば、親権を取れないケースもあります。
離婚したあと子どもは自動的に親権者の戸籍に入りますか?
子どもの戸籍は、離婚をしても自動的に変わることはなく、婚姻中の戸籍のままです。
また、親権者と子どもの氏が異なる場合、子どもは親権者の戸籍に入ることができません。
そのため、親権者が旧姓に戻った場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てて子どもの氏を変更してから、親権者の戸籍への入籍手続が必要です。
まとめ
親権は、未成年の子どもを育て、子どもの利益を守るために親が負う一切の権利・義務です。
現在の日本において、婚姻中は原則として父母が共同で親権を行使しますが、離婚する際には必ず父母のどちらか一方を単独の親権者として定めなければなりません。
親権者を決めるときに大切なのは、親自身の希望や感情ではなく、「子どもの利益」を最優先に考えることです。
これまでの監護状況や、子どもの年齢・心身の発育状況、離婚後の生活環境などを総合的に考慮して、親権者を取り決めましょう。
アディーレ法律事務所では、離婚に伴う親権に関するご相談を承っております。
「親権者になれるか不安」とお悩みであれば、まずは一度ご相談ください。
監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 慶應義塾大学法学部
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。