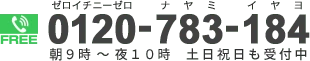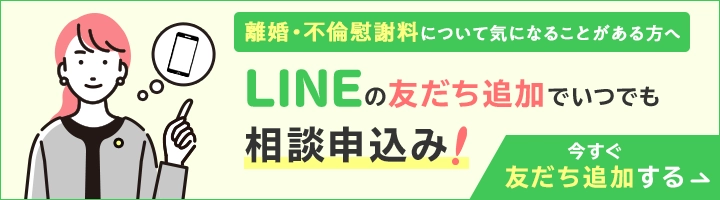離婚の公正証書とは?作成するメリットや手続の流れ、費用・必要書類を解説
夫婦の話合いで離婚することが決まった場合、「離婚協議書」を作成することで、離婚後の「言った・言わない」に関するトラブルを防げます。
一方で、離婚協議書には法的な強制力がありません。そこで、作成を検討するべきなのがより高い証明力をもつ「公正証書」です。
このページでは、離婚の公正証書と離婚協議書の違いや、公正証書を作成するメリット・デメリットに加え、実際の作成の方法や費用、必要書類などを詳しく解説します。
目次
このページでわかること
- 離婚の公正証書と離婚協議書の違い
- 離婚の公正証書を作成するメリット・デメリット
- 離婚の公正証書を作成する流れ・費用・必要書類
離婚の公正証書とは? 離婚協議書との違い
離婚の公正証書とは、離婚の合意内容を記載した、公正役場で公証人(法務大臣に任命された裁判官や検察官などを経験した有資格者)が作成する文書です。
離婚の際には「離婚協議書」を作成しますが、必要に応じて「公正証書」として作成することになります。
公正証書と離婚協議書は、離婚の合意内容を記載する点では同じです。
しかし、作成方法や効力に以下のような違いがあります。
| 離婚公正証書 | 離婚協議書 | |
|---|---|---|
| 文書の種類 | 公文書 | 私文書 |
| 作成場所 | 公証役場 | どこでもよい |
| 作成する人 | 公証人 | 離婚の当事者 |
| 作成費用 | かかる | 基本的にはかからない |
| 原本の保管方法 | 公証役場に保管される | 当事者が一部ずつ保管する |
| 証明力 | 高い | 公正証書より低い |
| 法的な強制力 | ある(※) | ない |
※執行受諾文言付の公正証書を作成した場合
離婚の公正証書を作成するメリット・デメリット
離婚の公正証書を作成すべきか判断するために、メリット・デメリットを知っておきましょう。
公正証書のメリット
離婚の公正証書を作成する主なメリットには、以下の3つが挙げられます。
- 証明力が高い
- 強制執行ができる
- 紛失・改ざんの心配がない
公正証書は高い証明力を持った文書であるため、離婚後に約束が守られない場合にも、スムーズに法的手続をとることができます。
離婚協議書を公正証書にしない場合、離婚後に養育費や慰謝料が支払われないときは裁判手続をとるほかありません。
しかし、あらかじめ執行受諾文言(「約束を守らないときは強制執行を受けてもよい」という条項)を付けて公正証書を作成しておけば、裁判をせずただちに相手の財産を差し押さえられます。
また、公正証書の原本は、公証役場で原則として20年間保管されるため、紛失や改ざんなどの心配もありません。
公正証書のデメリット
一方で、公正証書を作成することには以下のようなデメリットもあります。
- 時間やお金がかかる
- 夫婦で公証役場に行く必要がある
- 公証人に離婚の事情を知られる
公正証書を作成する際は、必要書類をそろえ夫婦2人で公証役場へ行き、公証人と面談をしなければなりません。
また、財産分与や養育費などの金額に応じた手数料もかかります。
時間やお金、労力がかかる点は、デメリットといえるでしょう。
また、公正証書を作成するために、離婚に関する情報はすべて公証人に伝える必要があります。
公証人には厳重な守秘義務があるため、夫婦の情報が口外されることはありませんが、なかにはデメリットに感じる方もいらっしゃるかもしれません。
離婚の公正証書は必要?作成を検討すべきケース
基本的に、離婚協議書は公正証書として作成しておくのがおすすめです。
一方で、公正証書を作成しなければ離婚できないというわけではないため、夫婦によっては、離婚協議書のみを作成するという判断もあり得ます。
しかし、以下のようにお金に関する約束をしているケースでは、公正証書の作成を検討すべきでしょう。
長期にわたり養育費を受け取るケース
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまで長期間にわたって受け取るお金です。
特に、幼いお子さまがいる場合には、10年以上にわたり受け取ることになります。
養育費の支払いが滞ってしまうと、お子さまの生活に影響がでてしまいかねません。
より確実に養育費を受け取るためには、公正証書を作成しておいたほうが安心でしょう。
執行受諾文言を付けて公正証書を作成しておけば、万が一支払いが滞った場合にも、相手の財産をただちに差し押さえられるため安心です。
高額な財産や慰謝料を受け取るケース
財産分与や慰謝料として高額なお金を受け取る場合、公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。
公正証書を作成しておけば、より確実に財産や慰謝料を受け取れるようになり、金額の改ざんなども防げます。
執行受諾文言を付けた公正証書を作成しておくことで、万が一約束どおり支払われないときにも差押えが可能です。
高額な慰謝料を分割払いにするケースなどには、特に公正証書を作成するメリットが大きいでしょう。
年金の合意分割を受けるケース
年金の合意分割を行う際は、原則として夫婦(またはその代理人)が2人揃って年金事務所へ行き、手続をしなければなりません。
しかし、公正証書があれば、年金分割を受ける方が1人で手続できます。
離婚後に元配偶者と予定を合わせて手続するのは、思った以上に面倒です。
年金分割をする側の配偶者にとってはメリットのない手続であるため、連絡がとれなくなることもあり得ます。
確実かつスムーズに手続するためにも、あなたが合意分割を受ける場合には、公正証書にしておきましょう。
離婚の公正証書の作成費用と必要書類
離婚の公正証書を作成する際には、費用や書類の準備が必要です。
以下で、作成にかかる費用と必要書類をまとめていますので、参考にしてみてください。
公正証書の作成に必要な費用
公正証書の作成費用・送達費用等は、取決めた養育費や財産分与などの金額に応じ、法令によって以下のように定められています。
| 金額の合計 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 49,000円+5,000万円まで超過ごとに15,000円 |
| 3億円を超え10億円以下 | 109,000円+5,000万円まで超過ごとに13,000円 |
| 10億円以上 | 291,000円+5,000万円まで超過ごとに9,000円 |
参考:日本公証人連合会「公証人手数料」
また、年金の合意分割について公正証書を作成する場合、別途13,000円の手数料が必要です。
なお、このほか公正証書の送達や送達証明などにも費用がかかります。
個別の事情によってさまざまな手数料がかかることもあるため、あらかじめ公証役場に確認しておいたほうがよいでしょう。
公正証書の作成に必要な書類
離婚の公正証書を作成する際には、主に以下の書類が必要です。
| 書類名 | 必要性 | |
|---|---|---|
| 公正証書の原案(離婚協議書) | 必須 | |
| 戸籍謄本 |
離婚前: 家族全員が記載された戸籍謄本 離婚後:それぞれの戸籍謄本 |
必須 |
| 本人確認書類等 |
以下のいずれか
|
必須 |
| 年金手帳など年金番号がわかる資料 | 年金分割を行う場合 | |
| 不動産の登記簿謄本および固定資産税納税通知書など | 不動産の所有権を移す場合 | |
具体的な取決め内容やご事情によっては、ほかにも書類が必要な場合があります。あらかじめ、公証役場に確認しておくとよいでしょう。
離婚の公正証書を作成する流れ
離婚の公正証書は、大まかに以下の流れで作成します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①合意内容をまとめる
公正証書を作成するためには、夫婦が離婚や離婚条件に合意している必要があります。そのため、まずは夫婦で話合いを行いましょう。
話合いがまとまったら、合意内容をまとめた公正証書の原案(離婚協議書)を作成します。
②公証人と打ち合わせをする
原案が作成できたら、公証役場に作成依頼の予約をします。
公正証書は、全国どこの公証役場でも作成できますが、実際に足を運ぶ必要があるため自宅などから近い場所を選ぶのが一般的です。
予約をしたら、実際に公正証書を作成する日までに、公証人と打ち合わせを行い、離婚協議書の内容をチェックしてもらいます。
なお、公証役場によっては、メールやFAXによる打ち合わせが可能な場合もあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
打ち合わせの内容をふまえ、公証人が公正証書を作成します。
③公正証書に署名・捺印する
公正証書の内容に合意する場合は、実際に公正証書を作成し受け取る日(調印日)を決めます。
調印日に夫婦がそろって公証役場へ行き、署名・捺印を行ったら、公正証書は完成です。
完成した公正証書の原本は、公証役場で原則として20年間保管されます。
夫婦には、原本と同じ効力をもつ正本(謄本)が交付されるため、大切に保管しておきましょう。
離婚の公正証書の内容
離婚の公正証書には、以下のように書くべきことと書けないことがあります。
公正証書に書くべきこと
公正証書には、以下の内容を記載します。
- 離婚協議の合意内容
- 住所や連絡先変更の通知義務
- 強制執行受諾文言
それぞれ詳しく見ていきましょう。
離婚協議の合意内容
離婚協議の結果、夫婦で合意した内容を漏れなく記載しましょう。具体的には、以下の内容です。
- 離婚に合意したこと
- 詳細な離婚条件
- 清算条項 など
詳しくは、離婚協議書について解説したページを参考にしてみてください。
住所や連絡先変更の通知義務
離婚後は、お互いに住所や勤務先、連絡先などが変わる可能性があります。
その際、相手側に変更の通知をすることを定めておくことも可能です。
たとえば、養育費などを受け取る場合に、相手の連絡先がわからないと支払いが滞ったときの請求手続ができません。
そのため、変更の通知を義務化しておくと安心でしょう。
強制執行受諾文言
強制執行受諾文言とは、「約束どおり慰謝料や養育費を支払わなかった場合、財産を差し押さえられても異議はない」といった強制執行を承諾する一文です。
この文言があることで、約束に違反して金銭の支払いをしなかった場合などに、公正証書に基づいて裁判をせず、ただちに相手の財産や給料などを差し押さえられるようになります。
合意内容に執行力をもたせることが公正証書を作成する大きな目的でもあるため、必ず記載しておきましょう。
公正証書に書けないこと
公正証書には、法律上無効なことや公序良俗に反することは書けません。
たとえば、以下のような内容です。
- 親権者を変更しないこと
- 養育費の金額を変更しないこと
- 子どもとの面会交流を一切認めないこと など
このほか、金銭の支払いが滞ったときの遅延損害金に対し、利息制限法を超える高い金利を設定することなどもできません。
離婚の公正証書の作成は弁護士に依頼するべき?
漏れなく離婚条件の取決めができており、適切な公正証書の原案(離婚協議書)が作成できているのであれば、夫婦だけで公正証書を作成できます。
一方で、そもそも話合いが難航している場合や、適切に公正証書の原案を作成できるか不安な場合には、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、配偶者との交渉や公正証書の原案の作成だけでなく、公証人との調整や公証役場での手続を代わりに行ってもらえます。
法律事務所によっては、公正証書の原案(離婚協議書)の作成のみを依頼できる場合もあります。
弁護士費用はかかってしまいますが、適切かつスムーズに手続を行うことができ、時間的・精神的な負担も減るでしょう。
離婚の公正証書についてよくある質問
離婚の公正証書について、お客さまからよく寄せられるご質問にお答えします。
公正証書の作成費用は誰が支払いますか?
公正証書の作成費用は、一般的に「公正証書を作成することで利益を得る側」が負担します。
たとえば、妻が夫から慰謝料や養育費を支払ってもらうケースでは、公正証書作成によって利益を得るのは妻です。そのため、妻が公正証書の作成費用を負担することになります。
ただし、夫婦で合意できれば、折半することや相手方に全額負担してもらうことも可能です。
また、場合によっては離婚原因を作ったほうの配偶者が負担するケースや、収入が多いほうの配偶者が負担するケースもあり得ます。
公正証書の作成を拒否されたらどうすればよいですか?
配偶者の合意なく公正証書を作成することはできないため、まずは最低限、離婚協議書を作成するよう話し合いましょう。
なお、「お金をかけたくない」という理由で拒否されたのであれば、作成費用を負担することで了承してもらえるかもしれません。
「手続が面倒」という理由であれば、弁護士に依頼し手続を任せることも可能です。
どうしても作成に応じてもらえない場合、離婚調停を申し立てることも検討しましょう。
調停が成立すれば、法的強制力のある「調停調書」が作成されるため、公正証書は必要ありません。
公正証書の内容は変更できますか?
原則として、公正証書の撤回・変更はできません。
ただし、当事者双方の合意があれば、新たに公正証書を作成することで変更が可能です。
例外として、養育費に関する取決めは、裁判所に養育費請求調停を申し立て、「事情が変わった」と認められれば、合意がなくても変更できます。
なお、親権者を変更したい場合は、公正証書や合意の有無にかかわらず、必ず親権者変更調停を申し立てなければなりません。
離婚後でも公正証書を作成できますか?
公正証書に作成期限はないため、元配偶者が同意すれば離婚後でも作成できます。
ただし、元配偶者が作成に応じてくれるとは限りません。
また、財産分与・慰謝料・養育費などを請求する権利には時効や期間の制限があるため、離婚後、何年も経ってから取り決めようとしても請求できる期限を過ぎてしまっているおそれもあります。
そのため、できるだけ離婚するタイミングで作成しておきましょう。
まとめ
離婚の公正証書は、高い証明力を持っています。
公正証書を作成しておけば、離婚後に約束が守られない場合に、スムーズに法的手続をとることができるため安心です。
特に、離婚後に養育費や慰謝料などを受け取る場合には、公正証書を作成しておくメリットは大きいといえます。
作成に費用や手間はかかりますが、ぜひ公正証書の作成を検討してみてください。
監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 慶應義塾大学法学部
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。